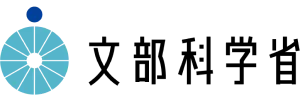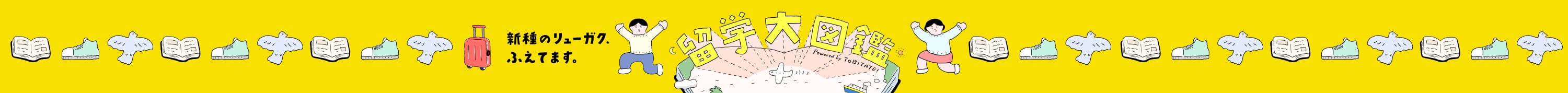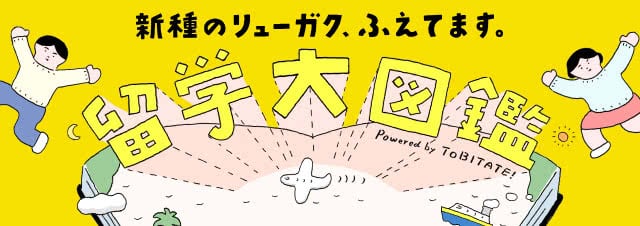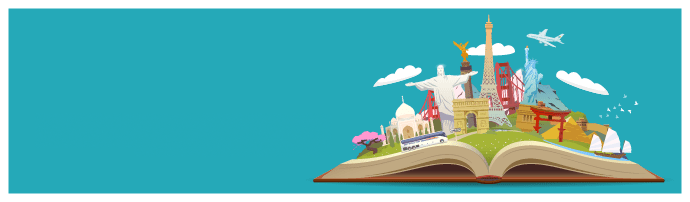留学内容
留学先では教授の下、「岩盤斜面の非破壊検査機器を用いたハザード評価」というタイトルで研究を行った。岩盤斜面は常に崩落の危険にある。近年、そのハザード評価は非破壊検査装置を用いて行われるようになってきており、東工大にない機器を備えたマラヤ大学で非破壊検査装置の使い方や使い方を中心に学んだ。基本的には、岩石の斜面や岩石の性状を評価するための非破壊検査装置を実際に使って、使い方や仕組みを理解し、担当教授にそのプレゼンを行い議論をしたのち次の器械に進むという流れで進めた。 本来は岩盤現場を訪問し、機器を使って危険度を予測する予定だったが私の担当教授が行っている岩盤調査プロジェクトは、関係者以外は簡単にアクセスすることができず、実際に岩盤を訪れて調査を行うことはできなかった。それでも、実際に数種類の非破壊検査装置を使用し、その使い方や原理を習得することができた。岩盤だけでなくコンクリートにも使用できる器具が多かったため、主にコンクリートに対して使用した。来年4月より建設業界で働くことが決まっており、扱う機会も多くなるであろう将来に向けいい経験になった。以下に具体的な内容を示す。
【課題と経過】
最初の課題は、マレーシアと日本で土砂災害の危険リスクがどのように評価されているかを調査することだった。土砂災害には大きく分けてがけ崩れ、地滑り、土石流の三種類がある。マレーシアにおいてはその種類によらず斜面の高さ、角度、地質などの観点からリスクをスコア化するという手法が一般的である。対して日本は三種類それぞれに起こりやすい地形があることを利用し、地形図で危険な個所を特定したのち斜面と民家などへの距離などを測りながら丁寧に算出する。どちらにも一長一短があり、日本の方法は丁寧だが時間がかかりすぎる。マレーシアの方法では簡単にできるがその精度は日本のに比べ低い。例えば、地形図判読でリスクが高い地域を日本の方法で特定したのち、マレーシア流のスコアシートを使う、など日本とマレーシアの方法を組み合わせれば精度を保ったまま効率を高めることができるかもしれないと感じた。
【成果】
その後、数種類の非破壊検査装置を実際に使い、使い方や原理を学んだ。具体的には、TLS(地上レーザースキャン)、ウォールスキャナー、鉄筋さび探知機、鉄筋探知機、Imapact Echo、UPV(超音波パルス速度)、リバウンドハンマー、GPR(地中レーダー)、AE(アコースティックエミッション)の9つの機器である。これらはコンクリートにのみ使える機器もあるが、岩盤を評価できるものも含まれ、使ってみてその精度や原理を学び、斜面崩壊のリスクを評価するのに非常に役立つことを実感した。特にTLSは盤斜面の破壊危険度を評価するために最も有効な器械の一つである。物体の空間的な位置情報を取得する計測装置でレーザー光線を対象物に当てて往復させ、距離や角度を測定する。1秒間に100万本以上のレーザービームが照射され、点群データとして測定結果が得られる。点群データは空間座標(x、y、z)で記録され、照射された物体の形状に関する正確なデータを提供する。このことは岩盤斜面など危険な場所のデータをそこに立ち入らずとも安全な位置から取得できることを意味し、岩盤斜面リスク評価に際し極めて有効な器械である。実際に装置を使う予定だったが、教授のスケジュールの都合でそれはかなわなかった。とはいえ、オンラインで実際の使い方の講習を受け、点群データを瞬時にかつ正確に取得できることを目の当たりにし、岩盤斜面の評価をより少ない時間と少ない人数でできることを学んだ。結論、実際の岩盤を見学することはできなかったが、岩盤斜面のハザードアセスメントに使用できる非破壊検査機器の原理や使い方を学ぶことができ、もともと自分で設定していた「岩盤斜面の非破壊検査による斜面崩壊危険度評価」というタイトルにふさわしい研究を行うことができた。英語でコミュニケーションをとらなければならない環境を含め、かけがえのない研究経験となった。