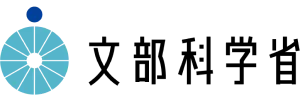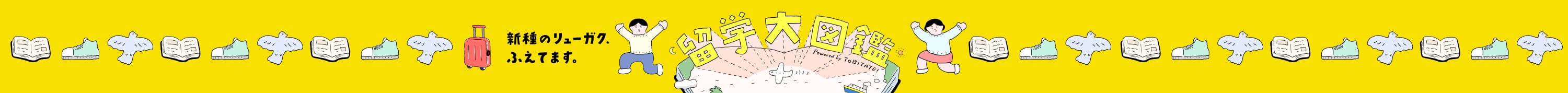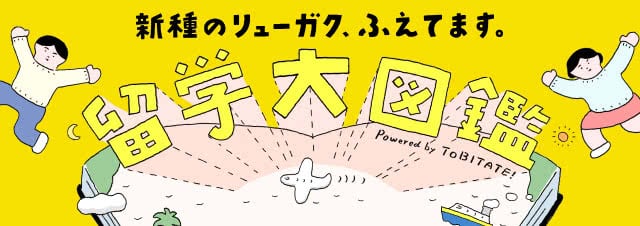インド(フンスール)
チベット仏教最大の宗派であるゲルク派の中でも密教を専門にするギュメ学堂と呼ばれる僧院に留学しました。在家用の寮で暮らし、食事や生活を在家チベット人と共にしました。勉強は、在家用のクラスと僧侶用のクラスの双方に出席しました。
授業は朝の7時にはお経を唱えることから始まって、8時には朝食(チベットのパレーと呼ばれるパンを食べます)、9時から12時まで授業、昼休憩があって、13時から19時まで授業と問答といった詰め込み教育を受けました。日中には、経典の暗唱、論理学の定義の暗唱、討論の筋書きの訓練などを重ね、夕方には問答で腕試しをするという繰り返しでした。休みの日もほぼ外出せず、勉強に勉強を重ねました。
授業や日常の全てがチベット語で行われました。授業以外でもチベット語を上達させたいために、英語で親切に話してくれるチベット人には、ガー・インジー・ヤゴ・シェング・メー(私は英語はよく分からないのです)と言って、会話の全部をチベット語で行いました。チベット語は言文一致をしていない言語で、文語しか日本では勉強していませんでした。なので、留学初期は、チベット語の聞き取り、口語の砕けた表現の理解に苦しみましたが、授業に出席するうちにわかるようになりました。さらに、留学前は楷書体(ウチェン)のみを知っており、文字の筆記体(キューイー)がわかりませんでしたが、筆記体も練習を重ねスラスラと読めるようになりました。加えて、チベット僧院の問答の実態は日本でほとんど知られておらず、研究の積み重ねもなく予備知識がない状態で行きましたが、僧院の先生方のおかげですぐ構文ややり方を習得することができました。
僧院は一種の社会で、さまざまな役職や上下関係があります。高位の僧侶にあった場合には五体投地といって土下座のようなことをする必要があります。僧院の序列の把握や人間関係についても学ぶことができましたし、それに応じた敬語などの言葉遣いも学びました。さらに、チベット人の独特な仕草(例えば偉い人に椅子を勧められたら舌をペロリと出して座るなど)についても学ぶことができました。
留学中の授業で学んだことは、仏教哲学、仏教論理学、チベット語文法学でした。仏教哲学では、仏教の学派を毘婆沙師、経量部、唯識、中観という四つに分け、それぞれの教義(grub mtha')を学びました。論理学では、ドゥラと呼ばれる文献に基づき、問答をしたり、ローリクと呼ばれる認識論を学び、それについても問答をしました。その後、『現観荘厳論』に基づいた般若学の最初を学ぶことができましたが、般若学に入ったあたりで留学期間が終了して帰国することになりました。チベット語文法学では、ヤンチェンドゥペードルジェと呼ばれる文法家の解釈に従ってチベットの文法学を学びました。いくつかの教科では暗唱が求められ、チベット語母話者ではない私にも母話者同様のテストが課され苦労しましたが、何度も書いたり、唱えたりすることで、暗唱試験にも通過することができました。チベット僧院のカリキュラムで言えば、極めて初歩的なことを学んだにすぎないので、この基礎をもってより高度な内容を将来的には、チベットの師僧に師事して学んで行きたいと思っています。
留学中に学んだ内容はnoteというブログに掲載していますので、是非ご覧ください(例えば:https://note.com/inuimasataka/n/naefdab1a3559)。