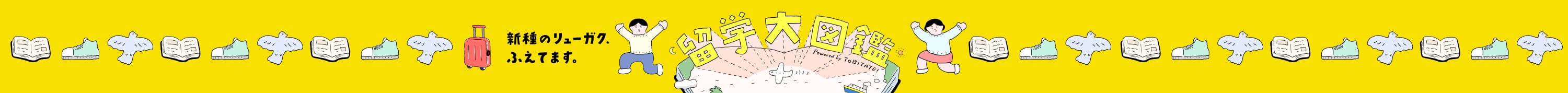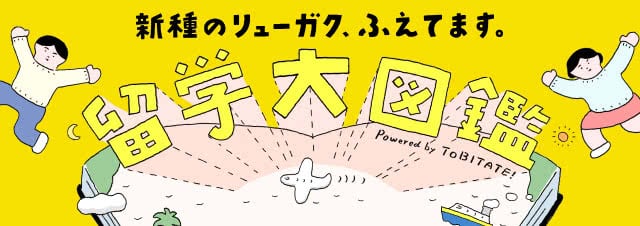フィリピン(セブ島)
一日のスケジュールとしては、8時に起床し、ホテルでトビタテの仲間と朝食をとり、9:30頃から私たちの活動をサポートしてくれる現地の大学生と一緒に活動場所(Mountain スラム、City スラム、墓地、Seaスラム、マザーテレサ修道院など)に行き、ボランティアを行いました。昼食は、活動先の近くにあるショッピングモールで取りました。その後、午前とは別の活動先に行き、4時くらいまで自分の探究活動やアンバサダー活動に励みました。そして、1日の活動が終了すると、トビタテ生のみんなでショッピングモールに行ったり、ホテルのレストランで夜ご飯を食べたりしました。疲れてなかなか勉強ができない日もありましたが、毎日1時間は学校の課題に取り組むように心がけていました。そして、1日の振り返りを含め、日記を書いて11時ごろには就寝していました。以下、具体的に、それぞれの活動先で行ったことを書きます。
Mountain スラム:ここでは「幸せ」とは何かの意識調査を子ども・大人に対して行ったり、食育を行ったりしました。
このスラムでは多くの人が住んでいたため、家を訪問して何が困っているのか、子どもたちの教育に対する思いを約30人にインタビューすることもできました。意識調査の結果を分析してみたり、インタビューでの意見を振り返ってみると、やはり多くの人が「家族の幸せ」を一番に考えていて、家族の絆の強さを感じることができました。
食育は、小学生の女の子10人くらいに「セブンイレブン」さんから提供していただいた「cycle-me」と日本で作っていった食育のプレゼンテーションを通して、五大栄養素について教えました。みんな「楽しい!」と笑顔で学んでくれました。
アンバサダー活動もこのスラムで行いました。日本の運動会の中からパン食い競争を伝えました。具体的には、地元のパン屋さんで菓子パン50個を購入し、持参したポリ袋にひとつずつ小分けにして、洗濯ものを干すロープに輪っかのついた洗濯バサミを通し、パンの袋を挟みました。活動先で出会った日本人の友達や、現地でサポートをしてくれたフィリピンの大学生の協力を得ながら、ルールを説明し行ないました。日本のように列に並ぶなどの習慣があまりなく、「よーいどん!」がなかなかできなかったことに、文化の違いを感じました。
Cityスラム:ここでは、主に算数を教えることを中心に行いました。他のスラムと比べて、Cityスラムは、かなり貧困で苦しんでいる人が多いスラムであり、家の仕事の手伝いがあるため、学校に行けない子どもたちが多かったのでこのスラムで算数を教えることを決めました。3週間のうち、2週間は、毎日3時間程、30人くらいの子どもたちを対象に教えました。最初は、九九ばかりか、足し算、引き算もなかなかできない子が半分ほどいましたが、私が直接教えたり、算数が得意な子が不得意な子に教えてあげたりした結果、最終日に簡単な算数のテストを実施すると、約25人の子どもたちが満点を取るようにまでなりました。嬉しいことに、私が教えた九九の歌をみんなで練習して、すべての子が7の段まで言えるようになっていました。みんな、算数の問題をまるでおもちゃで遊ぶように解いてくれる姿は、とても感動的で嬉しかったです。
中国人墓地:ここでは、算数と子どもたちに対して勉強へのアンケートを行いました。Cityスラムよりは、学校に通える子どもたちも多く、私が持っていった九九の問題をものすごく早く解く子もいました。ここで強く感じたのは、スラムと言っても、貧しさなど様々なスラムがあるということです。勉強へのアンケートは主に、科目の好き嫌いや勉強で困っていることを聞きました。勉強で困っていることとしては、文房具がない、英語がすらすら読めず他の科目も時間がかかる(フィリピンでは、4年生からはすべての科目で英語が利用されるようになるため)などでした。フィリピンの子どもたちが欲しいものは、必ずしもスマートフォンなど高価なものが欲しいわけではなく、文房具など勉強ができるものが欲しいということに驚きました。これからは、そうしたことも含め、支援のあり方を考えるきっかけとなる出来事でした。
Seaスラム:ここでは、主に英語教育を行いました。他のスラムよりも英語を読むことが苦手という子どもたちが多くいて、英語を話せない子も少なくなかったからです。本の読み聞かせや子どもたちと音読を行い、英語を楽しく読む機会を作りました。それに加えて、aとeなどのスペリングミスがあったので、ホワイトボードを使って、英語しりとりを行いました。遊びながら英語を使うことで、子どもたちは「楽しい!」と言って、スペルを覚えてくれました。このスラムの家は、海の上に木の枝を組み合わせて作っており、かなり劣悪な環境で暮らしをしているということが印象的でした。台風の影響を強く受けることや火事も多々あるらしく、建て替えが必要ですが、お金がないということで多くの人が日々危険な思いをしていることに、衝撃を受けました。
特別支援学校:フィリピンの教科書を見たいと思っていた私は、夏休みでも行われている特別支援学校に行きました。私立であるため、設備は日本と同じように、冷房もあり、安全安心な環境が整っていました。みんな英語で算数、体育の授業を受けていました。
マザーテレサ修道院:ここは、お金がなく苦しい生活をしている老人や親がいなかったり、貧困で障がいを抱えている子ども達にご飯を提供したりと無償で弱い立場にある人を支援する施設でした。私も手伝いとして老人にご飯を提供したり、食器洗いをしたり、子どもたちとボールで遊んだりしました。しかし、冷房もなく、大変でした。
8月6日 平和記念式典への参加:第二次世界大戦では、フィリピンが日本の植民地となったこともあり、亡くなった多くの現地の人、日本人を悼み、平和記念式典が行われていました。日本ではなかなか伝えられていない、日本軍の植民地への支配や特攻隊は、「神風特別攻撃隊」として1944年にフィリピンで始まったことを知り、驚きと悲しみを感じました。私は、広島出身ですが、自分の国の歴史ですら、他の国にいってみて初めて知るということに、自分の無知さを思いしられる8月6日となりました。
ゴミ山のスラム:フィリピンには、スカベンジャーといい、ゴミ山からゴミを漁り、生計を立てている人がいます。空気汚染がひどいため、ゴミ山のスラムで活動できるのは1日だけと決められていました。実際に、ゴミ山のスラムに近づいてみると、道路が汚染水で満たされていました。ゴミ山のスラムに住んでいる大人たちに理由を聞くと、「ゴミによる影響かもしれないけれど、正直わからない。怖くて、子どもを学校に連れて行かせられない」と言う返答が返ってきました。貧困問題が引き起こす、汚染問題について考えさせられた1日でした。
休みの日
オスロブツアー:休日には、セブ島の美しい海に行きました。トビタテの仲間と一緒に、ジンベイザメと泳いだり、ビーチではしゃいだりしてとても楽しかったです。活動していたスラムから約2時間あまりで行くことができ、同じセブ島なのにも関わらず、かなりの貧困格差を感じることとなりました。
シラマ神社・シラオガーデン:セブ島の有名なプライベート神社であるシラマ神社とインスタ映えすると有名な美しい花の公園であるシラオガーデンに、トビタテの仲間と現地のツアーを利用して行きました。自分で、行き方を調べ、専用タクシーを呼び、道中、セブ島についてたくさん話したことはとても良い思い出です。シラオガーデンは、噂通りとても綺麗で、たくさん写真を撮りました。タクシーの人は、帰りもとても親切で、セブ島の美味しい魚料理の店を教えてくれたりしました。現地の観光は、日本人用のツアーを使わず、現地の人の行き方で行くのも楽しいと思いました。