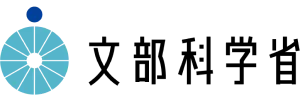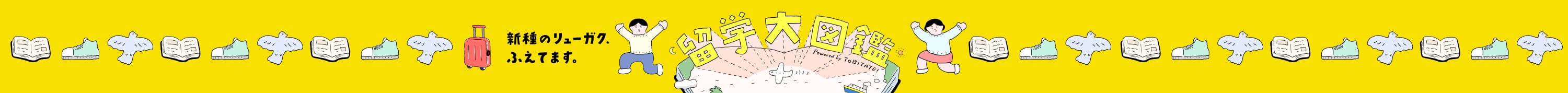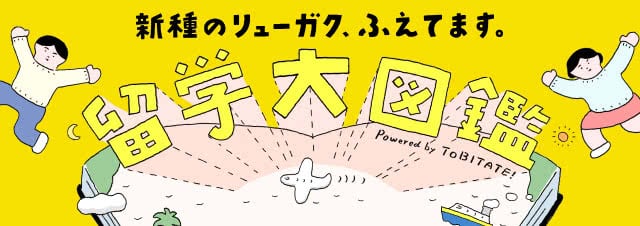留学内容
現代社会では災害の頻発が問題となる中、私は「最後の一人まで取り残さない」「被災者が主体的に生きることができる社会」の実現を目指し、被災者の視点に立った研究と実践活動を行うことを目的に留学しました。具体的には、2023年2月に「世紀の大地震」とも称されたトルコ・シリア地震が発生したトルコで、“災害の実践”に関する研究を深めました。ボアズィチ大学では、トルコで最も歴史があり、最先端の地震研究・教育機関であるカンディリ天文台地震観測所の防災研究所(AHLAB)のメンバーと協力し、防災教育と社会認識に関する論文や書籍を共同執筆しました(いずれもトルコ語)。また、被災地では、教育複合施設で防災教育と映像・文章・芸術を通じた集団的記憶の保存に関するボランティア活動を行ったほか、被災者の経験がどのように災害認識や災害実践に影響を与えるか、被災を巡る裁判の動向、さらには早急な復興活動に伴う環境問題など、被災後の社会におけるさまざまな課題について調査を行いました。これらの活動を通じて得た重要な気づきは、トルコでは1999年のコジャエリ地震以降、震災に強い街づくりや意識向上が強く求められ、法制度改革や教育などさまざまな取り組みが行われてきたということです。しかし、復興を名目に利益追求が最優先されることで、脆弱な建物の建設が進み、それに伴うコンクリート工場や採石場の設置が加速しています。これにより、環境問題や健康被害が発生し、災害や破壊の悲劇が形を変えて繰り返される現実が浮き彫りとなりました。また、災害が単に制度や法律のみに起因するものではないことに気づきました。災害は、社会制度や人間の倫理など、さまざまな要素が複雑に絡み合い、相互に影響を与えながら形作られているのです。そのため、単に法整備や改革を行うだけでは不十分であり、人々の日常の小さな態度や言説、行動を、歴史や文化、社会などの多角的な視点から検討し続けることの重要性を学びました。