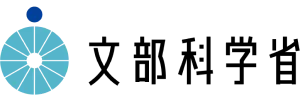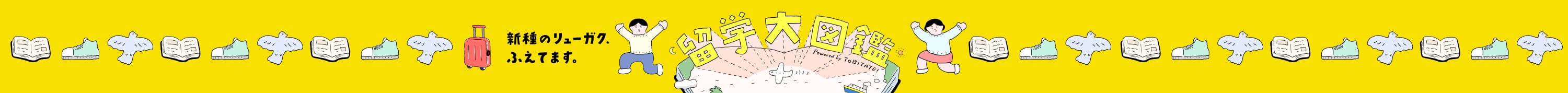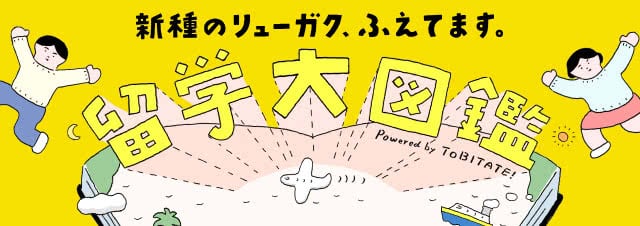ラオス(ルアンパバーン)
探究内容については留学内容にとことん書いたので、ラオスでの生活や魅力について記していく。
私が活動拠点にしたルアンパバーンは、街全体が世界遺産に登録されている都市で、旅人界隈では「東南アジア最後の秘境」とも呼ばれている。メコン川の流れるその街は、赤い屋根の家屋と、美しい自然、歴史のある寺院が見事に融合している。食べ物やお土産の並ぶナイトマーケット、朝の托鉢体験、安価なマッサージなどを楽しめる。道沿いの小さな半家屋で手織りの織物を作っている様子がよく見られる。ハンドメイド製品が並ぶ店内も工夫が凝らされていて美しい。留学中、「世界一何もない首都」と呼ばれるラオスの首都ビエンチャンや、自然を楽しむ観光アクティビティが溢れる都市バンビエン、不発弾など、ベトナム戦争による傷跡が遺る地域シェンクワンなど、他の都市にも訪れたが、ルアンパバーンは自分が一番好きな街だと感じた。乾季・雨季があり、気候は普通に日本くらい暑い。渡航したのが雨季だったので、急に雨に降られたり雷がひどい時もある。
食べ物については、チリや薬草が入っているため辛いものが多いが、日本人の口に合っていてとても美味しい。もち米が主食で、竹籠に入ったもち米を手に取って食べるスタイル。それをほぼ毎日食べていたおかげか、自分は日本食が恋しくなることはなかった。コーヒー栽培も盛んなので、観光客向けのおしゃれなカフェがたくさん街に並んでいる。元々フランスの植民地だったため、パンも美味しい。私のお気に入りのご飯は、カオピャック(米粉でできた麺料理)、シンダート(焼肉と鍋が融合したもの)、ラープ(ひき肉炒め)、パパイヤサラダ。物価は日本より若干安いくらいでほとんど変わらないが、フルーツだけは激安。マンゴー1個が100円なので、毎日食べていた。
途上国のわりに治安が良く、渡航中のトラブルはほとんど自分のミスだった。街中にトイレが少なかったり、村の中に置き水と穴しかないトイレしかない時は困った。人口が少ないので交通渋滞もなく道路も静か。都市部のインフラはほとんど問題なく、道路も整備されている。ただ、農村部に行くと環境がガラッと変わり、未整備で水たまりだらけの道路になる。中国鉄道の開通など、急速に開発が進んでいるが、意外なことに人々は街の発展に対してあまり肯定的ではないらしく、自然のある生活を求めてわざわざ農村に移住する人もいる。一方で、農村部の貧しい若者がやむなく都市部へ稼ぎにくることも多い。あとは、自分の滞在する場所でダニが大量発生し、家の中や自分の足がひどい状態になった時があった。毎日のルーティンとしてダニをろうそくで焼く作業をしていた。
ラオスは多民族国家で、同じラオスに住んでいても母語が違うことが多い。(ラオ族と、その他諸々の民族って感じで、「ラオ達」→Laosになったらしい。)みんながまず公用語としてのラオス語を学ぶので、英語が話せる人が少ないのがすごく困った。そういう言語の壁はジェスチャーやカタコトのラオス語、翻訳機で乗り切った。向こうもそれを理解しようと努力してくれる優しい人が多い。共食文化という、一緒に食卓を囲み食べ物を共有する文化がある。近くに居れば知らない人だろうが誰でも呼んできて、一緒に食べ物を食べる。ゆるい生活スタイルで、穏やかで謙虚な人が多い。