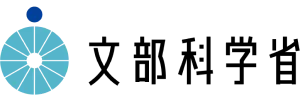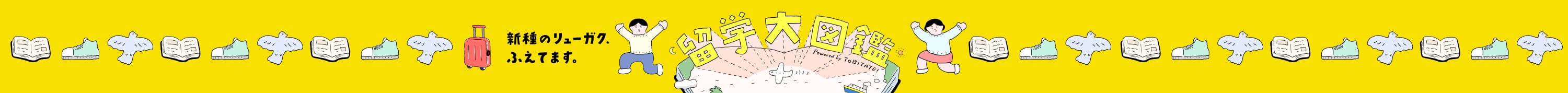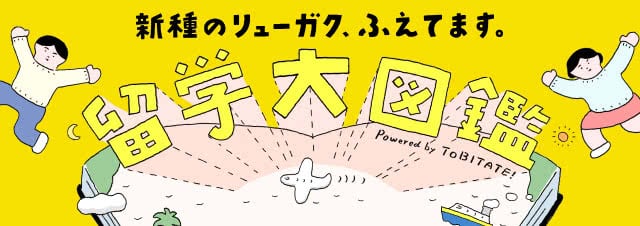留学内容
国際協力に関心のある私は、ルワンダで日本人が関わる2つのNGOでインターンをしながら、JICAの支援現場も訪れました。キガリ滞在中は、義肢製作所を運営するNGOのゲストハウスに宿泊し、自炊をしながら活動しました。
1つ目のインターン先は、1994年のルワンダ大虐殺直後から30年間、義足を手作りし、紛争や事故、病気で手足を失った人々に無償で義肢や杖を提供しているNGOです。日本人女性のルダシングワ真美さんとルワンダ人のパートナー、ガテラさんのもとで、広報インターンとして16日間活動しました。義手の受け渡しに立ち会い、地方巡回診療の資金調達ミーティングへの同席、告知ポスターの作成を通じて、広報が支援活動の継続に果たす役割について学ぶことができました。
2つ目のインターン先は、JICAが支援する私立小学校で、5日間の授業インターンを経験しました。海外青年協力隊の先生と教材を手作りしたり、音楽の授業ではピアノ伴奏やピアニカ指導、日本の歌を紹介しました。絵画の授業では、子どもたちに将来の夢を描いてもらいました。農村でホームステイをした際、地域の小学校を訪問し、日本の文化を紹介しました。2つの学校訪問を通じて、ルワンダの初等教育の現場の現状を見ることができました。また、ルワンダ政府の教育機関NESAを訪問し、教育政策についてのインタビューも行いました。
さらに、JICAの支援について学ぶため、JICA事務所でのインタビューを行い、JICAが支援する若者向けスタートアップ拠点「K-Lab」や、デジタル製造支援の「FabLab」も訪問しました。これにより、日本のODAがICT立国と言われるルワンダの発展にどのように貢献しているのかを知ることができました。
ルワンダのジェノサイドから30年という節目に、当時の様子を知る義肢装具所の真美さんに紛争メモリアルを案内していただきました。