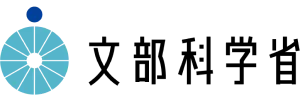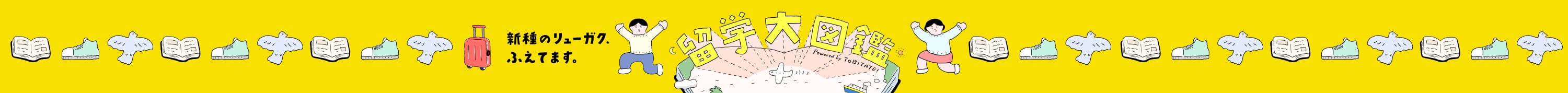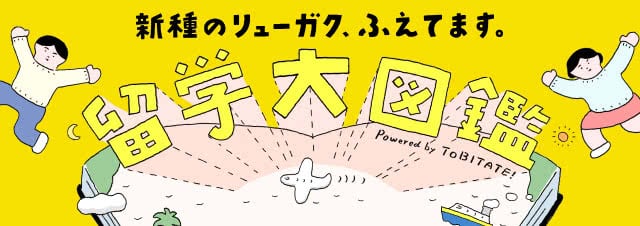留学前に一番磨くべきは言語

トキオ( 済美高等学校)
- 留学先(所属・専攻 / 国 / 都市):
-
- ニューヨークフィルムアカデミー
- アメリカ合衆国
- ロサンゼルス
- 留学テーマ・分野:
- 短期留学(3か月以内、語学・ボランティアなど各種研修含む)・専門留学(スポーツ、芸術、調理、技術等)
留学をする際には是⾮、できるだけ英語⼒をアップしてから挑戦して欲しい。トビタテ⽣たちには外国⼈たちに負けない、⾼い志と能⼒を持っている。でも、それを表現するための英語⼒がなければ、留学先で実⼒を認められないことがあるから。海外にいったら英語⼒が上がるだろうという考えではなく、留学前に出来る限り英語⼒をあげる努⼒をしてほしい。特に磨いておくべきなのは文法だと思う。リスニング力や発音などは留学してからできるようになっていくが、逆に文法などは疎かになってくる。出発までに文法を磨いておくことで、実際にそれを留学先で使った際にしっかりと自分のものとして身につき、なおかつ自信を持ってプレゼンや発表をすることができる。
続きを見る