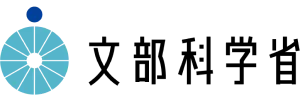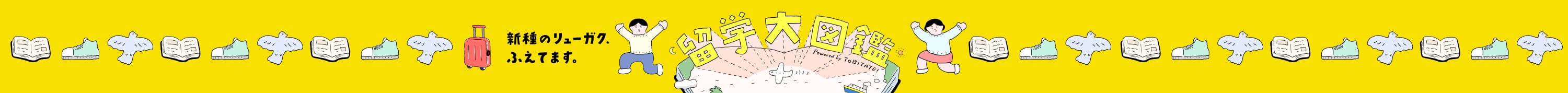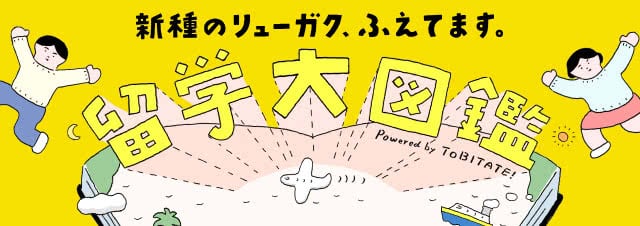必死でもがく友人に後押しされて

カノ(京都工芸繊維大学/ 金沢泉丘高校)
- 留学先(所属・専攻 / 国 / 都市):
-
- ケルン応用科学大学
- ドイツ
- ケルン
- 留学テーマ・分野:
- 大学院生:交換・研究留学(日本の大学院に在籍しながら現地大学院内で学ぶ留学)
私のスタジオは英語で行うことが多かったのですが、他のコースを取得していた留学生は全てドイツ語、更にコースの留学生が一人という中で物凄いスピードでドイツ語を習得していました。私はそれどころか英語も他の留学生より劣っていると感じ、自分が不甲斐なくてしょうがない一方、会うたびにドイツ語は話せるようになる友人に後押しされ、「英語ごときで躓いてたらダメ、私もドイツ語やる」と全くゼロの状態から無謀にも大学の初心者コースと並行してドイツ語を独学で習得し始めました。建築・英語・ドイツ語のトリプルスタディはなかなかハードでしたが、友人に「ドイツ語できるようになってる、いいじゃん!」と励まされるのがすごくモチベーションになり、お互いレベルは違いましたが、最大限高め合えました。(最終的には日常会話レベルは習得しました)
続きを見る