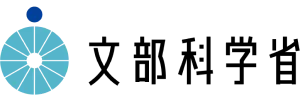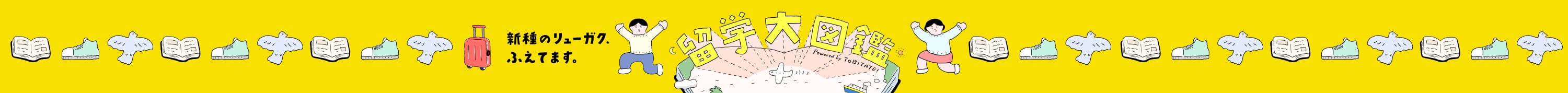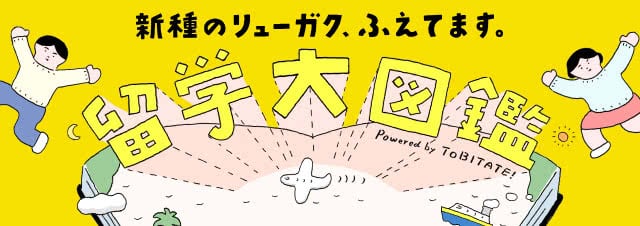周りに頼る!

ふうか( )
- 留学先(所属・専攻 / 国 / 都市):
-
- Celtic English Academy
- イギリス
- モンマス
- 留学テーマ・分野:
- 短期留学(3か月以内、語学・ボランティアなど各種研修含む)・語学留学
私は最初デンマークなど北欧への留学を考えていたのですが、良いプログラムや探究活動が見つからなかったので周囲の大人とか友達に頼って人員を増やして探しました。最終的に私が行ったプログラムは親が見つけてくれたものです。あまり課題という課題がないまますんなりと留学に行けたので、特に解決法やアドバイスが書けなくて恐縮ですが、周りに全力に頼るといいよ!というのは言えるかなと思って書きました。
続きを見る